-
20220117
京都から自宅に戻る。ソフトキャリーにあるものを荷ほどきするまでが旅。夕食を軽く食べたのちすぐに寝る。なんだか変…
-
20220116
1月16日。今週の疲れが出たのか8時間も寝てしまう。目覚めてコーヒーを淹れる。普段は豆から挽いているが、ホテル…
-

20220115
1月15日。昨日の雪はもう見えなくなっていた。朝、ゆっくりとクロワッサンとコーヒーを飲みながら考える。歴彩館ま…
-

20220114
1月14日。外はちり紙を小さくちぎったような雪が降っていた。その軽さに世界から重力が少し失われたかのようだ。ぎ…
-
20220113
1月13日。木曜日。2年前のことになる。やらなければならない研究についてテクストを書いていた。お世話になってい…
-
20220112
1月12日。部屋で工作をしていて。それはソフトキャリーのタイヤを修理することだった。けっこうすり減っていたので…
-
20220111
2021年1月11日。火曜日。この日記は昨日アップするつもりだったが、手元にあるMacbook Airの調子が…
-
20220110
1月10日。月曜日の祝日。宅配便が2つ届く。ひとつは玄米、もうひとつが鴻池さんの個展で展示した手紙。玄米から米…
-
20220109
1月9日。日曜日。曇と晴が混じるはっきりしない天気、食パンを焼く。焼いたものをさらにオーブンで焼いてカリリとし…
-

20220108
1月8日。土曜日。知人に誘われて都現美で「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」をみる。…
-

20220107
朝、タブレットで新聞を読みながらコーヒーを飲む時間が、一日のエンジンをかける時間になっている。朝光がびたびたに…
-

20220106
特別快速の電車に乗る。停まる駅よりも停車しない駅の方が多く、ただ風景が流れていく。電車のなかで話をしているふた…
-
20220105
1月5日。夜はひきつづき『ショア』をみている。まだ第一部。監督のクロード・ランズマンがユダヤ人の連行を目撃した…
-
20220104
1月4日。昨日の夜、風呂あがりに『ショア』の続きを見はじめるが30分もしないうちに瞼が重くなる。第一部の途中で…
-
20220103
1月3日。浮かれるような気持ちが衰えて、日常がむっくりゆっくり立ち上がってくる時間が漂っている。昨日の夜からク…
-

20220102
口絵 深沢七郎『楢山節考』昭和32年、中央公論社 新年の二日目、1月2日はいつも何かがゆっくりと始動しようとす…
-
2022年はじまり、はじまり
これまでツイッターでは日報としてひとつのツイートだけで完結させていたけれど、今年からはこちらに戻ろうと思う。理…
-

身体を光で切り刻む — 宇佐美圭司の芸術
7月2日、雨の日。東京大学駒場博物館の「宇佐美圭司 よみがえる画家」を訪問する。 わたしは東大の史料編纂所や明…
-

ある女性と自由
昨今の黒人や女性の人権、香港における言論の自由といったことについて、思い出したことがある。 日中戦争で戦死した…
-

重力をつきぬける — 齋藤陽道『感動、』
齋藤陽道『感動、』(2019)より フョードロフにとって重力とは原罪に似ていて、人類を下方へ、大地へ、横臥状態…
-

わたしの2010年代
本棚とルイ・ブライユの胸像写真 2019年の年末。今年は2010年代を総括した一年であるといえる…
-

平成の思い出 ー 恋と嘲笑
今日で元号としての平成が終わる。 わたしにとって、ひとつの元号を生きるというのは初めてのことだ。 けれども、昭…
-

少し開いた戸の向こう側 — 志村信裕《Nostalgia, Amnesia》(2019)
国立新美術館で配布された、21st DOMANI・明日展の配置図・出品リストを見て、志村信裕の展示場所を確かめ…
-

ブルー・カーペットと六畳間
新年、あけましておめでとうございます。今年もライブラリー・ラビリンスをよろしくお願いします。 年末年始、ち…
-
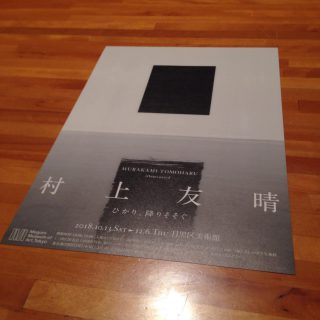
紙をかき分ける — 村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」
村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」を見る。 これは絵画というよりは、一人の織りかさなる祈りのように思えた。 村上…
-

風景の分解不可能性 — 「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」
「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」にて ワタリウム美術館にて「Hyper La…
-

背中の思い出 あるいは、思い出の背中 — 村瀬恭子
村瀬恭子《In The Morning》 (1998、村瀬恭子展にて(ギャラリーαM)) ときお…
-

筒井茅乃とヘレン・ケラー
今日は8月9日。 アメリカのボストンにあるパーキンス盲学校のアーカイヴスにはヘレン・ケラー宛への手紙が多数デジ…
-

長谷川利行と東京市養育院
長谷川は人生の最後で倒れ、行病人として東京市養育院に入院した。 胃がんだったという。養育院から矢野文夫に手紙を…
-

偶発の組成 — 地主麻衣子「欲望の音」
Art Center Ongoing「53丁目のシルバーファクトリー」にて HAGIWARA PROJECTS…
-

思い出の触覚 − 椋本真理子「in the park」
国分寺のswitchpointへ。 椋本真理子の作品には、ニュートラル、非場所性、人工、といった言葉を思い浮か…
-

蟹を埋める
2018年3月16日。夜に買ったアサリを砂出しをするべく、塩水に浸す。 2018年3月17日。朝、アサリの砂が…
-
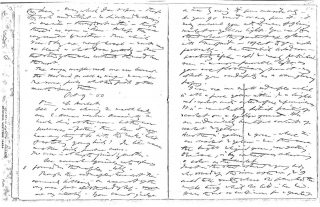
木を見るときに
“You cannot judge a tree by seeing it from one si…
-

瑞々しさの基準
宮城県・多賀城市にて。 何かに対する判断基準として、それが瑞々しいかどうか、というのがある。 ある機関で史料調…
-
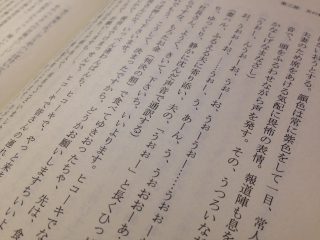
もぎとった果実のように、声を手渡す — 石牟礼道子
石牟礼道子『苦海浄土』『神々の村』『天の魚』を読了する。言わずと知れた、水俣を描いた三部作。 樹木から果実を取…
-

かろやかな人
危口さん。久しぶり。 昨日、京都の家に帰宅したあとに危口さんが亡くなったことを知った。今日がお通夜で明日は…
-

2016年
夢殿観音(明治時代・小川一眞撮影) 年末年始、帰省までの切符を受け取った瞬間、2016年の瀬を感じることになっ…
-

トランス/リアル - 非実体的美術の可能性 vol.5 伊東篤宏・角田俊也
誰かを抱いた時。 子供のころ、父や母に抱きついた時。愛おしい人に抱きついた時。 胸や背中が膨張を繰り返して呼吸…
-

岡山芸術交流 会場情報・アクセスについて
岡本太郎「躍進」(岡山駅にて) 岡山芸術交流においては、各会場の作品の配置を示したパンフレットが配布されていま…
-

瞼の非同期とインサーション
画像はαMギャラリーウェブサイトより αMギャラリーでトランス/リアル - 非実体的美術の可能性 vol.4 …
-

京都府立総合資料館と京都盲唖院
京都府立総合資料館の投書箱。 ときどきおもしろい投書がある。 一番笑えたのは「熊のプーさんは爬虫類ですか?」と…
-

歪んだ柱
広島。長崎。わたしは今年、原爆が落ちた街を訪れた。 いろいろと思うことはあるが、長崎の興福寺というお寺を訪れた…
-

瞽女の声
momatの吉増剛造展に。吉増が収集してきたカセットテープの束を見ていたら、瞽女に関するものが7本もあった。杉…
-

盲人と自分を見つめる
momatの常設展に中村彝が描いたエロシェンコの肖像画がある。常設ではスタメン、登場する確率が高い絵画である(…
-

光の集合と終わり — 志村信裕《見島牛》
六本木クロッシング2016を訪問する。オープニングに伺って以来、しばらく見る余裕がなかったが、終了間際になって…
-

刻まれる写真 — 東松照明の長崎
ちょうど、わたしは長崎で史料調査をしていた。わたしは全国の盲人・聾者の社会とコミュニティを盲唖学校を通じて研究…
-

道後温泉にて
長崎、宇和島、松山と調査が続いていたので、息抜きをしたく、道後温泉本館に。松山では有名な観光地でまあベタなとこ…
-

ニカッと笑う小西信八
小西信八が笑っている写真は珍しい。盲唖学校での集合写真ではこのような表情は見せない。嬉しいことがあったのだろう…
-

犀星の初版本グラフ
資料を整理していた時に出てきたもの。金沢にある室生犀星記念館でもらったのだと思う。本の装丁と出版年をグラフにし…
-

断章 ー 出窓の先に
新居に越してもうすぐ一年になろうとしている。出窓からの風景を見ながらコーヒーを飲んだり、朝食をとるのが楽しいの…
-

部屋と欅
用事があり、旧居に行かなければならなかった。 わたしがかつて住んでいた居室の様子をみると、窓のある部屋に切り倒…
-

手の重さ、部分の記憶体 — サイ・トゥオンブリ
1週間近く、雨や曇りが続いていたけれども、金曜日になって夏の日射しが感じられるようになった。サイ・トゥオンブリ…
-

窓の脇で
先生。まだ先生の背中は遠いよ。
-

手形付き・足形付き土製品(大石平遺跡 青森県立郷土館蔵)
惹かれるなあ。 手形付き・足形付き土製品 大石平遺跡 青森県立郷土館蔵 粘土に子供の手や足を押しつけて焼き上げ…
-

最後の手段《おにわ》
(画像は有坂亜由夢さんのタンブラーより) イメージの祖父。 祖父のイメージ。 老いた男性が棺桶らしいものに包ま…
-
盲人の視覚
雪ふかみ たはめど折れぬ 呉竹の 色やゆるがぬ 御代とこそしれ この歌は、小杉あさという近代の静岡において東海…
-
台湾歴史博物館の常設展示
台湾歴史博物館の常設展示。特徴的なのは、ジオラマが多いことであろうか。説明というよりも体験的な内容。そのジオラ…
-
島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展
去年12月、台湾歴史博物館で1999年9月21日の震災をテーマにした展覧会「島嶼‧地動‧重生:921地震十五周…
-
來自四方:近代臺灣移民的故事特展
去年12月、台南の国立台湾歴史博物館で移民をテーマにした「來自四方:近代臺灣移民的故事特展」という、近代から現…
-
2014年の展評
年の瀬となりました。2014年に見た展覧会のなかで、心に残ったものをいくつか選んでみます。 1、内藤廣 「アタ…
何かおすすめの本はありますか ?